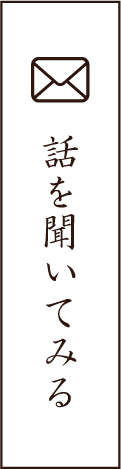工事日誌
ヒートショックを防ぐ家づくり——健康と断熱の関係
おはようございます。
10月も半ばになり、朝晩は少しずつ冷え込みを感じるようになってきましたね。
これから冬にかけては、体調を崩しやすい季節。
そして、毎年この時期から増え始めるのが「ヒートショック」による家庭内での事故です。
これまでこのブログでは「断熱」「窓」「耐震」「気密」と、住まいの性能についてお伝えしてきました。
今回はその延長として、「健康と断熱の関係」、そして「ヒートショックを防ぐ家づくり」についてお話しします。
寒さの本番を迎える前に、家の“温度”を見直すきっかけにしていただければ幸いです。
- ヒートショックとは?
「ヒートショック」という言葉、冬になるとニュースなどでも耳にする機会が増えます。
ヒートショックとは、急激な温度差によって体に負担がかかる現象のこと。
たとえば、
暖かいリビングから寒い脱衣室へ移動して衣服を脱ぐと、
血圧が一気に上昇します。
その後、熱いお風呂に入って血管が急に拡張すると、今度は急激に血圧が下がる——。
この血圧の乱高下が、心筋梗塞や脳出血など命に関わる事故を引き起こすことがあります。
実際、厚生労働省の統計によると、冬季の入浴中の急死者数は交通事故死の数を大きく上回るとも言われています。
そして、私たちの住む静岡県は、このヒートショックによる事故件数が全国でも上位に位置しています。
「静岡は温暖だから大丈夫」と思われがちですが、
冬の朝晩は意外と冷え込み、日中との寒暖差も大きいのが特徴です。
そのため、家の中の温度差が生まれやすく、油断すると**“温暖地ゆえのヒートショックリスク”**に直面してしまうのです。
- なぜヒートショックは起きるのか?
原因はシンプルです。
それは、家の中の温度差。
古い住宅や断熱性能の低い家では、
- リビング:20℃
- 廊下:10℃
- 脱衣室・浴室:5〜8℃
というように、10〜15℃もの温度差が生まれることがあります。
この温度差が、身体に大きなストレスを与えます。
特に高齢者は血圧の調整機能が低下しているため、
その変化に体がついていけず、意識を失うケースも少なくありません。
静岡県内でも、冬場の入浴事故や浴室での突然死が増加傾向にあり、
「冬季の住宅内で10℃以上の温度差がある住宅が約7割」というデータもあります。
つまりヒートショックは「雪国の問題」ではなく、
静岡のような温暖地でも日常的に起こりうる住宅の課題なのです。
- 温度差のない家が「健康」を守る
ヒートショックを防ぐ最大の方法は、
家の中の温度差を小さくすることです。
たとえば高断熱・高気密住宅では、
リビングも脱衣室も廊下もほとんど同じ温度に保たれます。
暖房を止めても外気の影響を受けにくく、
家全体が“魔法瓶のように”穏やかな温度で包まれているのです。
つまり、断熱とは「寒さ対策」だけではなく、
命を守るための“健康装置”でもあるということ。
実際に、高断熱住宅に住み替えたご家庭では、
- 冬の血圧が安定した
- 手足の冷えが軽減した
- 起床時の体調が良くなった
など、健康面での改善を実感する方が多くいます。
- 断熱と健康の関係——科学的な裏づけ
近年、「住宅の断熱性能と健康」の関係は明確に研究で示されるようになってきました。
- 断熱改修後の健康改善データ
国土交通省の調査(スマートウェルネス住宅等推進事業)によると、
断熱改修を行った家庭では、
- 血圧が平均で4〜5mmHg低下
- 咳・のどの痛み・関節痛などの症状が減少
- 冬場の室温が平均2.5℃上昇
という結果が得られています。
特に高齢者の健康改善効果が顕著で、
「住宅の断熱性能が健康寿命を延ばす」ことが明らかになっています。
- 室温18℃が健康の基準
WHO(世界保健機関)は、
**「冬季でも居室の室温は18℃以上を保つべき」**と勧告しています。
それ以下では、呼吸器疾患や血圧上昇のリスクが高まるとされています。
つまり、快適なだけでなく“安全な住環境”のためにも、
住宅の断熱性能は健康基準のひとつなのです。
- ヒートショックを防ぐための設計ポイント
① 断熱の連続性を確保する
壁・天井・床・窓を“途切れずに”断熱材で包み込むことが重要です。
どこか1か所でも断熱ラインが切れると、そこから熱が逃げ、温度差が生まれます。
これを「熱橋(ヒートブリッジ)」と呼びます。
② 樹脂サッシと建物・窓配置の工夫
家の中で最も熱が出入りするのは“窓”です。
冬場に熱を取り込める窓は樹脂サッシ+複層ガラスを採用し、熱を取り込めることが期待できない窓は樹脂サッシ+トリプル硝子を採用します。
熱を取り込める窓というのは南側の窓のこと。ただし冬場になるべく日影にならない窓。
なるべく日影にならない窓にするために隣地の状況から敷地にできる日影を読み解きなるべく日影の時間が短いように建物を配置することも必要です。
③ 計画換気と気密性能
断熱が良くても、家の隙間から冷気が入れば台無しです。
気密性能(C値)を確保することで、安定した室温が保たれます。
また、気密が取れていれば換気計画も正確に機能し、
家全体の空気が均一に入れ替わります。
④ 空調計画——全館空調や床下エアコンの活用
最近では「小屋裏エアコン」「床下エアコン」など、
少ない熱源で家全体を快適に保つ空調方式も増えています。
これらは高気密・高断熱の住宅だからこそ成立する設備であり、
室内の温度ムラをなくすことでヒートショック防止に大きく貢献します。
- 奏建築工房の考える“静岡の健康住宅”
奏建築工房では、
ヒートショックを防ぐための基本性能として、
- UA値0.4以下
- C値0.7以下
を標準仕様としています。
静岡のように一見“温暖”に思える地域こそ、
冬場の温度差が発生しやすいのが実情です。
私たちはこの地域性を踏まえ、
「冷えをつくらない家」「どの部屋も同じ温度で過ごせる家」を目指しています。
これにより、
「冬の朝でも室内温度が安定する」
「廊下や脱衣室も寒くない」
「冷暖房費が大幅に減る」
といった効果をもたらします。
断熱材は、屋根には高性能グラスウールに押出法ポリスチレンフォームで付加断熱、
壁にも高性能グラスウールに押出法ポリスチレンフォームで付加断熱、
基礎には押出法ポリスチレンフォームを採用。
加えて、全棟で気密測定を実施し、施工精度を数値で確認しています。


- 断熱は“家族の健康保険”
ヒートショックを防ぐ家づくりは、
単に「快適さ」や「省エネ」の話ではなく、
家族の命を守るための備えです。
冷えは万病のもとと言われるように、
住宅の温熱環境は、私たちの体温や免疫力にも深く関係しています。
断熱性能を高めるということは、
言い換えれば「毎日を安心して過ごせる家をつくる」ということです。
そしてその性能は、
建築基準法の“最低限の基準”を超え、
暮らしの質を守る基準へと変わりつつあります。
- まとめ——“あたたかさ”は最高の安全装備
ヒートショックを防ぐ家とは、
どの部屋にいても温度差が少なく、安心して過ごせる家。
それを実現する鍵は「断熱」と「気密」、そして「空調の設計」です。
- 静岡はヒートショック事故が全国でも上位
- ヒートショックは家の温度差が原因
- 室温18℃以上を保つことが健康の基準
- 高断熱・高気密・計画換気で温度差をなくす
- 奏建築工房ではUA値0.4・C値0.7以下を標準仕様に
季節が進むこれからの時期、
「暖かさ」は何よりの安心であり、健康を守るための“住宅性能”です。
静岡という温暖地だからこそ、
“ヒートショックを起こさない家”を意識した住まいづくりが求められています。
奏建築工房は、これから訪れる冬を前に、
この地域に暮らす皆さまが安心して過ごせる“健康な住まい”を一棟一棟丁寧にお届けしていきます。