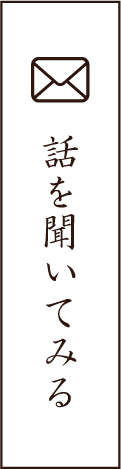工事日誌
第一種換気とは?——快適な空気をデザインする高性能住宅のしくみ
おはようございます。
これまでこのブログでは、断熱や気密、耐震、基礎など、家の「性能」についてお話ししてきました。
今回は、見えないけれど確実に暮らしを支えているもの——**「換気システム」**についてご紹介します。
なかでも、高気密高断熱住宅では欠かせないのが「第一種換気」。
「換気なんてどれも同じじゃないの?」と思われるかもしれませんが、
実は、家の快適さ・省エネ性・健康性に直結する重要な仕組みなのです。
1.換気の目的とは?
私たちは1日におよそ15,000リットルもの空気を吸って生活しています。
住宅の中では、
- 人の呼吸による二酸化炭素
- 家具や建材から発生する化学物質(VOC)
- 調理・入浴による湿気
- ハウスダストや花粉
などが溜まりやすく、思っている以上に空気がよどみやすい環境です。
これらを外へ排出し、常に新鮮な空気を取り入れるのが換気の役割。
つまり「換気」とは、家の空気を入れ替え、健康と快適を守るしくみです。
2.換気方式の種類
換気システムには大きく3つの方式があります。
種類 給気・排気の仕組み 特徴
第1種換気 給気・排気の両方を機械で制御 換気量が安定し、熱交換が可能
第2種換気 給気を機械、排気を自然換気 特殊環境(クリーンルーム等)で使用
第3種換気 給気は自然、排気のみ機械 一般住宅に多い・低コスト
多くの住宅では第3種換気(トイレや浴室の換気扇など)が使われていますが、
高気密高断熱住宅では第一種換気が最適とされています。
3.第一種換気とは?
第一種換気は、給気も排気も機械でコントロールする換気方式です。
外の空気をファンで取り入れ、室内の空気を別のファンで排出。
その際、空気の流れ(どの部屋からどの部屋へ動くか)を設計段階で決めておくため、
常に計画的・効率的な換気が行われます。
さらに多くの機種が「熱交換換気(全熱交換型)」に対応しています。
これは、排出する空気の熱を回収し、その熱を利用して外気をあらかじめ温めて(または冷やして)から取り込む仕組み。
その結果、換気による室温の変化を最小限に抑えることができます。
4.第一種換気のメリット
- 室温が安定し、省エネ
全熱交換型では、排気時の熱エネルギーの約70〜90%を回収可能。
冬でも外気をある程度温めて取り入れるため、暖房効率が上がり、省エネ性が高まります。
- 空気がクリーンで健康的
給気口には高性能フィルターが設置され、花粉・PM2.5・黄砂などをカット。
外気を清浄化してから室内に送り込むので、常にきれいな空気が流れます。
- 冬でも乾燥しにくい
全熱交換タイプでは、湿気もある程度回収できるため、
外の乾燥した空気がそのまま入らず、加湿効果が長持ちします。
- 高気密住宅との相性が抜群
家の隙間(C値)が小さいほど、空気の流れが設計どおりにコントロールできるため、
C値0.7以下の高気密住宅では第一種換気の効果が最大限に発揮されます。
5.第一種換気の注意点
- 初期コストがやや高い(機器と配管施工費)
- 定期的なフィルター清掃・交換が必要(数か月〜半年に1回)
- 設計段階で換気ルートを考慮する必要がある
ただし、これらは“手間”ではなく、“安心して快適に暮らすためのメンテナンス”と考えるのがポイントです。
正しく設計・施工・管理されれば、非常に安定した空気環境を維持できます。
6.ダクト付きとダクトレスの違い
第一種換気には、実は2つのタイプがあります。
どちらも「給気・排気を機械で行う」という点は同じですが、空気の流し方と構造が異なります。
- ダクト付き第一種換気(集中型)
天井裏や床下にダクト(配管)を通して、家中の空気をコントロールします。
1台の熱交換ユニットで全館をまかなうため、温度ムラが少なく、静音性・省エネ性が高いのが特徴です。
新築時に導入するのが一般的で、奏建築工房でもこのタイプを採用しています。
メリット:
- 全館の換気が安定
- 熱交換効率が高く省エネ
- 空調と連動しやすい(小屋裏エアコン等)
デメリット:
- ダクト施工スペースが必要
- フィルター清掃が2~3カ月程度に1度発生
このデメリットを解消するためフィルターを予備でワンセット準備しておけばフィルターを交換して汚れたフィルターを水洗い→干す→保管とすれば水洗い自体は30分程度の清掃で完了します。また、フィルター交換はリモコン部分にメンテナンスランプが点灯しお知らせしてくれます。
- ダクトレス第一種換気(分散型)
壁に小型の換気ユニットを設置し、部屋ごとに空気を出し入れします。
ダクト工事が不要なため、リフォームや既存住宅への導入がしやすいのが大きな利点です。
仕組みとしては、一定時間で吸気・排気を交互に行い、そのたびにセラミック素子に熱を蓄え・放出することで熱交換を行います。
メリット:
- 施工が簡単(ダクト不要)
- メンテナンス性が高い(各部屋で清掃可)
- 既存住宅の断熱改修時にも導入可能
デメリット:
- 熱交換効率はダクト型よりやや低い(約70〜80%)
- 同期制御(吸排気のタイミング調整)が必要
7.第一種換気と第三種換気の比較
換気の種類 第一種換気 第三種換気
換気方式 給気・排気とも機械制御 排気のみ機械、給気は自然
熱交換 あり(全熱/顕熱) なし
室温への影響 少ない 外気の影響を受けやすい
フィルター性能 高性能(花粉・PM2.5対応) 簡易的
メンテナンス 定期清掃が必要 少なめ
コスト 高め 安価
つまり、家の性能が高いほど第一種換気が有効に働くということ。
断熱と気密をしっかり確保した住宅では、第一種換気の真価が発揮されます。
8.奏建築工房の換気設計
奏建築工房では、小屋裏エアコンとの相性を考慮し**全棟で第一種全熱交換換気システム(ダクト付き集中型)**を採用しています。
C値0.7以下の気密性能をベースに、空気の流れを一棟ごとに設計。
この流れを設計段階でコントロールすることで、室温のムラが少なく、空気がきれいな家を実現しています。
また、フィルターは花粉やPM2.5を除去できる高性能タイプを採用し、静岡でも発生するの花粉・黄砂・潮風の影響を最小限にしています。
9.まとめ——“見えない空気”が暮らしを左右する
第一種換気は、見た目ではわかりません。
しかし、毎日吸う空気の質を整えるという意味では、断熱や気密と並ぶ住まいの基本性能です。
- 室温を保ちながら換気できる
- 空気がきれいで健康的
- 冬でも乾燥しにくい
- ダクト型は全館向け、ダクトレスは改修向け
どちらの方式を選ぶにしても、正しい設計と気密性能の確保が前提となります。
奏建築工房では、「断熱」「気密」「換気」「空調」をひとつのシステムとして考え、
静岡の気候に合った“やさしい空気の家”をつくっています。