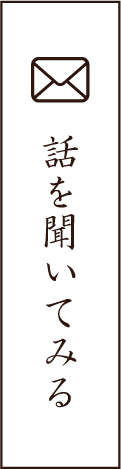工事日誌
木造住宅の「気密」とは何か?——心地よい住まいを支える“見えない性能”
 おはようございます。
おはようございます。
これまでこのブログでは「断熱」や「窓」、「耐震」についてお話ししてきました。
今回はそれらと並んで、快適な住まいをつくるうえで欠かせない「気密」についてお伝えします。
住宅の性能を語るとき、「断熱」と「気密」は切っても切り離せない関係にあります。
しかし「気密」と聞いても、ピンとこない方が多いのではないでしょうか。
「密閉された家なんて息苦しそう」「昔の家のほうが風通しが良くて健康的」――そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。
でも実は、それは“誤解”です。
本当の意味での「気密住宅」とは、ただ空気を閉じ込める家ではなく、必要な場所で、必要な空気を、計画的に流す家のことなのです。
気密とは何か?その目的を誤解していませんか?
まず、気密の目的を正確に理解しましょう。
気密とは、建物の隙間をできる限り減らして、室内と外気の無駄な出入りを防ぐことです。
たとえば冬。
せっかく断熱材で熱の逃げ道をふさいでも、壁の中やサッシまわりに小さな隙間があれば、そこから冷たい空気がどんどん入り、暖房で温めた空気が逃げてしまいます。
いくら断熱性能が高くても、隙間だらけの家では意味がないのです。
C値(相当隙間面積)という指標
気密性能を数値で表すものに「C値」があります。
これは、住宅全体の隙間の面積を延べ床面積で割った値で、**単位は㎠/㎡**です。
たとえばC値が3.0の家は、1㎡あたり3㎠の隙間があるという意味。
30坪(約100㎡)の家なら、家全体で300㎠、つまりはがき2枚分程度の隙間がある計算になります。
現在の一般的な住宅では、C値2.0~5.0程度が多いですが、高気密住宅では1.0以下を目標にします。
C値1.0というのは、延べ床100㎡の家で隙間が合計100㎠、つまりハガキ1枚の2/3程度です。
これはまさに「職人の精度」と「設計の整合性」が問われる世界です。
なぜ気密が大切なのか——3つの理由
① 熱損失を防ぎ、省エネ効果を高める
気密性が高いほど、冬の暖房・夏の冷房効率が上がります。
隙間からの空気漏れ、流入を防ぐことで、断熱材の効果を最大限に活かせます。
結果として、冷暖房費が削減されます。
② 壁内結露を防ぐ
気密が悪い家では、暖かい室内の湿った空気が壁の中に入り込み、壁内部で冷やされて結露を起こすことがあります。
この「壁内結露」は、断熱材の性能を落とし、柱や梁を腐らせ、カビやシロアリの原因にもなります。
つまり、気密は家の寿命を守る性能でもあるのです。
③ 計画換気が正しく機能する
現代の住宅には「24時間換気」が義務付けられていますが、家に隙間が多いと、換気システムが正しく働きません。
意図しない場所から空気が出入りするため、汚れた空気が部屋に滞留したり、給気口から十分な新鮮空気が入らなかったりします。
気密性が高い住宅では、計画どおりに空気が流れ、いつも室内がクリーンな状態を保てます。
高気密を実現するための施工ポイント
気密は設計だけでなく、現場での施工精度が最も重要です。
どんなに図面上で完璧でも、実際の現場での“少しのすき間”が性能を左右します。
主なチェックポイントは以下の通りです。
- コンセントボックスや配管まわりの気密処理
- サッシ枠と躯体の取り合い部の防水・気密テープ
- 天井・床の下地貫通部のシーリング処理
- 気密シートの重ねしろと留め方
気密施工は「最後にまとめてやる」ものではなく、工事の各段階で意識し続けることが大切です。
現場監督や大工さんの施工精度が問われる部分でもあります。
よくある誤解:「気密が高いと息苦しい?」
「そんなに密閉したら空気が悪くなるのでは?」という声をよく聞きます。
でもそれは誤解です。
気密を高めることで、むしろ空気はきれいになります。
なぜなら、前述のように「計画換気」がしっかり働くからです。
気密が低い家では、換気扇を回しても外気がどこからでも入るため、空気の流れが乱れます。
一方、高気密住宅では給気口→居室→排気口という理想的な空気の流れを実現できるのです。
気密測定を全棟で行う意義
奏建築工房では、すべての新築住宅で気密測定を実施しています。
これは「性能の確認」というよりも、家づくりの“品質保証”の一環だと考えています。
気密測定を行う理由は3つあります。
- 施工精度の確認と改善ができるから
気密測定では、実際に専用の測定器で家の中を減圧し、どの程度の空気漏れがあるかを数値で確認します。
結果が想定より悪ければ、その場で原因を探し、漏気箇所を修正します。
これにより、現場の気密施工レベルを確実に高めていくことができるのです。 - 棟ごとのバラツキをなくすため
家ごとに設計条件などが異なるため、気密性能にも差が生じる可能性があります。
全棟測定を行うことで、データを蓄積し、どの工程・材料・納まりが最も安定するかを検証できます。
こうした取り組みが、将来的に標準仕様全体の品質向上につながります。 - お施主様に“数字で見える安心”を届けるため
気密性能は目で見えない性能ですが、測定結果としてC値を報告することで、「自分の家がどのくらいの性能なのか」をお施主様自身が確認できます。
家づくりにおいて“感覚ではなく根拠”を示すことが、信頼につながると考えています。 - 設計だけでは気密の確保はできないから
気密は図面上の数値ではなく、現場での施工精度で決まる性能です。
どれだけ高性能な断熱材やサッシを採用しても、
コンセントボックスの隙間や梁まわりの処理ひとつで、実際の気密性能は大きく変わってしまいます。
つまり、設計段階で「C値7」と掲げても、それを実際に“現場で再現できているか”を確認する唯一の方法が気密測定なのです。
測定を行うことで、図面と現場の差異を見える化し、施工体制そのものの精度を向上させることができます。
測定は完成直前ではなく、主に断熱材施工後・仕上げ前のタイミングで行います。
この段階であれば、気密の不具合を発見した際に補修が可能だからです。
まさに「家づくりの健康診断」と言えるプロセスです。
設計だけで気密の数値を表現して、気密測定を行わないのは間違いなので注意してください。
当社が目指す気密性能と考え方
奏建築工房では、C値0.7以下を標準仕様として目指しています。
断熱と気密は「二つで一つ」。
断熱性能(UA値0.4以下)をしっかり確保するためにも、気密性能は欠かせません。
また、気密測定は全棟で実施します。
結果を数値で確認し、どの部分に漏気があるかを現場で共有し、再度補修する。
こうした地道な作業の積み重ねが、快適な住まいづくりに直結すると考えています。
気密の先にある「快適」という価値
気密性能は数字で表せますが、実際の暮らしで感じるのは「快適さ」です。
冬の朝、起きた瞬間に部屋の空気が冷たくない。
花粉やホコリが室内に入りにくく、空気が澄んでいる。
家の中の温度差が小さく、どの部屋も同じように暖かい。
それが高気密・高断熱住宅の真価です。
住む人にとって「気密」は見えない部分ですが、
その“見えない性能”こそが、毎日の暮らしの質を支えているのです。
まとめ
- 気密は「断熱性能を最大限に活かすための技術」
- C値0.7以下を目標にすることで、快適・省エネ・長寿命を実現
- 気密が高い家ほど、計画換気が正しく働き、空気がきれいになる
- 大切なのは設計だけでなく、現場での丁寧な施工と測定
見えないところにこそ、家づくりの本質があります。
奏建築工房では、これからも“数字に裏づけされた快適な住まい”を、一棟一棟丁寧に届けていきます。