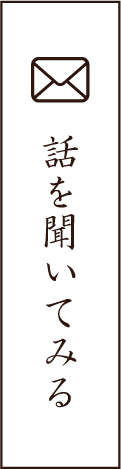工事日誌
木造住宅の「基礎」
おはようございます。
これまでこのブログでは、断熱・気密・耐震・換気などの性能面についてお話ししてきました。今回は家づくりの土台にあり、完成後はほとんど見えなくなるのに、家の寿命と安心感を大きく左右する存在、基礎について掘り下げます。
基礎は単なるコンクリートの塊ではありません。地盤と建物をつなぎ、荷重を受け止め、湿気や外気の影響から構造体を守り、温熱計画の土台にもなる総合的な“しくみ”です。見えないところにこそ、丁寧な設計と精度の高い施工が求められます。
1.基礎の役割は「荷重を地盤に伝える」こと
基礎の役割を一言で表すなら、
「建物の重さや地震時の力を、地盤に確実に伝えること」です。
建物には、
- 建物自体の重さ(固定荷重)
- 家具や人が加える重さ(積載荷重)
- 風や地震などの水平力(外力)
が常に作用しています。
これらの力を地盤へ逃がすことで、建物全体が安定し、傾きや沈下を防ぎます。
つまり基礎は「構造的な受け皿」であり、建物の性能を支える“力の通り道”なのです。
2.基礎の種類と選び方
現在の木造住宅で主流なのはベタ基礎です。状況により布基礎を使うケースもあります。
- ベタ基礎
建物の下全面を鉄筋コンクリートのスラブと立ち上がりで一体化し、面で支える構造です。荷重の分散性に優れ、不同沈下に対して安定しやすく、床下の防湿にも有利です。デメリットはコンクリート量が多くコストがやや上がることですが、耐震性・耐久性とのトレードオフを考えると合理的な選択です。ただし、しっかりとした構造計算されたべた基礎であれば大丈夫ですが計算されていないものに関しては注意が必要です。私たちは新築では許容応力度計算を行ったベタ基礎を基本としています。 - 布基礎
外周や主要な間仕切りの直下に帯状の鉄筋コンクリートを設ける構造です。コンクリート量や配筋量が少なく残土の処分も少ないので比較的ローコストですが、防湿や荷重伝達の観点で計画・施工に注意が必要です。べた基礎の時と同様にしっかりとした構造計算が必要になります。
3.コンクリートと鉄筋――品質を決める根本
基礎の性能は材料の品質と施工精度で決まります。特にコンクリート強度と鉄筋配筋は基礎の“骨と筋肉”に相当します。
- コンクリート強度の正しい理解
木造住宅では一般に Fc21〜Fc24(= 21〜24 N/mm²)のコンクリートを使用します。
1kgf=9.8Nなので、21〜24 N/mm² は おおよそ2.1〜2.4 kgf/mm² に相当します。
この数値は「1 mm²あたり約2.1〜2.4キログラム重の圧縮に耐えられる」という意味です。
面積でイメージすると、100 mm × 100 mm(10,000 mm²)の断面では、21 N/mm² × 10,000 mm² = 210,000 N、すなわち約21,000 kgf(およそ21トンf)の圧縮荷重規模に耐える強さです。
強度は配合(セメント量・水セメント比)やスランプ、打設時の気温、締固め、初期・湿潤養生の良否に大きく左右されます。冬季は低温で強度発現が遅れるため、適切な養生期間と凍害対策が必須です。静岡市近郊では凍害はあまりないと思いますが山間の現場であれば注意が必要になると思います。打設時期を踏まえて適切な養生期間の確保が重要になってきます。
- 鉄筋の配筋精度
鉄筋の径・ピッチ・定着長さ・継手位置、かぶり厚(鉄筋表面からコンクリート表面までの距離)は耐久性と耐震性を左右します。スペーサー(サイコロ)で鉄筋を正しい高さに保持します。立ち上がりと底盤の一体性、開口補強、隅角部の補強筋など、図面上の指定を現場で確実に再現することがポイントです。

4.地盤との“相性”が寿命を決める
どんなに強い基礎も、地盤が弱ければ安定しません。新築では必ず地盤調査(スクリューウエイト貫入試験など(以前のスウェーデン式サウンディング試験))を行い、地耐力・土質・推定地下水位を把握します。その結果に応じて基礎の形状・配筋を決めたり、必要に応じて地盤改良を行います。
代表的な改良は、表層改良(浅い層を固化)、柱状改良(地中に柱状体を造成)、鋼管杭(支持層まで杭で支持)などです。地盤改良は余計な費用ではなく、何十年も安心して暮らすための保険と考えるのがよいでしょう。
5.基礎と断熱
高性能住宅では、基礎は構造だけでなく温熱計画の要でもあります。床断熱と基礎断熱の考え方を整理します。
- 床断熱
床の裏側に断熱材を施工し、床下は外気を通気し床下を乾燥させる工法です。 - 基礎断熱
基礎の立ち上がりやスラブ側に断熱層を設け、床下を室内とほぼ同じ温度帯に保つ方法です。床下エアコンとの相性が良く、家全体の温度ムラや上下温度差の低減に有利です。断熱ラインと気密ラインを連続させる設計が重要で、基礎と土台、壁との取り合い処理が性能を左右します。
当社では、地域特性や住まい方を踏まえ、UA値0.4以下・C値0.7以下を目安に、基礎部分も含めて断熱と気密の連続性を重視した納まりを採用しています。

6.現場品質を高めるために
基礎は完成すると見えなくなるため、施工中の検査・記録が品質の生命線です。私たちは次のような管理を徹底しています。
・配筋検査(自主検査および住宅保険検査(ほぼ義務))
・かぶり厚・定着長さ・補強筋の実測確認
・コンクリート受入時の運搬時間・スランプ・空気量の確認
・打設手順と締固め、継目の処理、レイタンス除去
・養生期間の確保と温度管理、強度試験体の採取
・レベル出しと天端精度(一般に±3 mm以内)
・写真と数値の記録
こうした基本の積み重ねが、見えない安心を何十年も支えます。
7.まとめ――家の安心は足元から
基礎は建物の構造・温熱・耐久のすべてを支える静かな主役です。
適切な地盤評価、合理的な構造形式、正しいコンクリート強度と配筋、連続した断熱・気密、防湿と床下環境の管理、そして現場品質の徹底。これらがそろって初めて、上部構造の性能が生きてきます。
デザインや設備は目に見えて分かりやすい価値ですが、長く暮らすほどに効いてくるのは足元の品質です。私たちは、完成後には見えなくなるこの部分にこそ時間と手間を惜しまず、一棟一棟、確かな土台をつくり続けています。