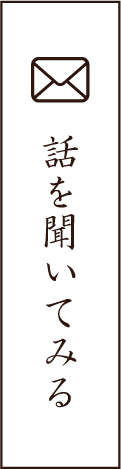工事日誌
断熱について
こんにちは。
これまでこのページでは主に現場での工事の様子や日々の出来事をご紹介してきましたが、今後はお施主様の家づくりに役立つ情報も少しずつ発信していきたいと思います。家を建てるときに多くの方が気になるテーマの一つに「断熱」があります。以前にも断熱のことについてはご説明したことがありますが今回はもうちょっと深堀して、できるだけわかりやすくお伝えしてみます。
断熱とは?
「断熱」とは、文字どおり“熱を断つ”ことを意味します。わかりやすい例を挙げると「冷蔵庫」です。冷蔵庫は中の食品を一定の温度で保つために、しっかりと断熱材で覆われています。扉を開けっ放しにすると冷気が逃げ、庫内の温度は下がらなくなってしまいますが、きちんと閉めていれば内部の温度を効率よく保つことができます。もし断熱が不十分なら、冷蔵庫は温度を保つために多くの電力を消費し、電気代も大きくなってしまいます。
住宅もこれと同じで、壁や屋根、床といった建物全体を断熱材で包み込むことで、外気温に左右されにくい室内環境をつくることができます。ただし、冷蔵庫と違い、住宅には玄関や窓など複数の開口部があり、生活の中で人の出入りや調理・入浴による熱や湿気の発生もあります。さらに、快適で健康的な暮らしを送るためには、計画的な換気も必要です。つまり、断熱だけでなく「気密」や「換気」とのバランスがとても大切なのです。
冬の暖かさと健康への影響
「断熱」と聞いてまず思い浮かぶのは、冬の寒さ対策だと思います。確かに、静岡は全国的に見ると比較的温暖な地域ですが、それでも冬の朝晩は冷え込みます。特にお風呂やトイレに移動する際の温度差によって起こる「ヒートショック」は、実は静岡県でも全国的に見ても上位の発生率で、多くの方の健康を脅かしています。
断熱性能の高い住宅は、家の中の温度差を少なくし、廊下や脱衣所も快適な温度に近づけることができます。これによってヒートショックのリスクを減らし、ご家族が安心して過ごせる住まいにつながるのです。特にご高齢のご家族がいる場合は、この点がとても大切になります。
夏の暑さにも強い断熱
静岡は冬だけでなく、夏の暑さも厳しい地域です。屋根は真夏の直射日光を受けると、表面温度が60〜70℃にまで上がります。その熱が室内に伝わると、エアコンを強く使わないと快適な温度を保てなくなり、光熱費がかさみます。
例えば、室温を27℃に設定しても、屋根の表面温度との差は40℃以上。断熱材が不十分だと、2階はどうしても蒸し風呂のように暑くなってしまいます。逆に、断熱性能をしっかり確保できれば、少ない冷暖房エネルギーで快適な温熱環境を保つことができます。
断熱性能を示す「UA値」
住宅の断熱性能を数値で表す指標として「UA値(外皮平均熱貫流率)」があります。
これは「建物全体の外皮から、1㎡あたり1℃の温度差でどのくらい熱が逃げるか」を示した値です。数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。
具体例を挙げます。仮に UA値=0.5 W/㎡・K の住宅で、外気温0℃・室温20℃に保ちたいとします。建物の外周面積を300㎡とすると、
0.5 × (20−0) × 300 = 3,000W
の熱が常に失われる計算になります。UA値が小さくなればなるほど必要なエネルギーは減り、エアコンの能力を過剰に大きくしなくても快適な室温を保てる、という仕組みです。
断熱材の種類と厚みの大切さ
断熱材にはさまざまな種類があります。例えば、
- グラスウール(コストパフォーマンスが高く、多く使われる)
- ロックウール(耐火性能に優れる)
- 吹付ウレタンフォーム(隙間なく施工できる)
- セルロースファイバー(調湿性能に優れ、エコな素材)
- ネオマフォーム(高性能フェノールフォーム)
- スタイロフォーム(押出法ポリスチレンフォーム)
断熱材の性能は「種類」だけでなく「厚み」でも大きく変わります。断熱材には「熱伝導率」という指標があり、値が小さいほど熱を通しにくくなります。
断熱性能を示す「熱抵抗値」は、
熱抵抗値 = 断熱材の厚み ÷ 熱伝導率
で求められ、厚みが厚いほど、熱伝導率が低いほど、性能は高まります。
例として、
- 高性能グラスウール16K(熱伝導率 0.038W/m・K、厚さ105mm → 熱抵抗値 約2.76㎡・K/W)
- ネオマフォーム(熱伝導率 0.020W/m/K、厚さ25mm → 熱抵抗値 約1.25㎡・K/W)
この比較からもわかるように、断熱材の性能を正しく理解するには、種類と厚みの両方を確認することが大切です。もし営業担当者が「ネオマフォームを使っているから性能が高いです」と説明しても、25mmしか入っていなければ十分な断熱効果は期待できません。ぜひ「厚みは何ミリ入っていますか?」と確認してみてください。
断熱の施工方法
断熱材の入れ方には主に3つの方法があります。
- 充填断熱(内断熱)
柱と柱の間に断熱材を充填する方法です。施工しやすい反面、柱部分には断熱材が入らないため、熱が伝わりやすい「熱橋(ヒートブリッジ)」が生じやすくなります。 - 外断熱
柱の外側を断熱材でぐるりと覆う方法です。柱部分も含めて外皮全体が断熱されるため、温熱環境はより安定します。ただし、外壁の厚みが増すため、敷地やデザイン上の制約が出る場合があります。 - 充填断熱+付加断熱
充填断熱と外断熱を組み合わせた方法で、断熱性能をさらに高めることができます。熱の逃げ道を塞ぎつつ厚みを確保できるため、快適性と省エネ性の両立が可能です。
当社では、この 付加断熱工法 を標準仕様としています。具体的には、壁には グラスウール16K(105mm)を充填断熱として採用し、その外側に ネオマフォームやミラフォームラムダを付加断熱しています。屋根については施工性の高さ、さらに 小屋裏エアコンを採用するため、小屋裏空間全体を断熱層に含める「屋根断熱」を選んでいます。野地板の内側に グラスウール16K(105+105mm)、外側に ネオマフォームまたはミラフォームラムダを組み合わせて施工しています。これにより、夏の暑さにも冬の寒さにも強い快適な住まいを実現しています。
断熱で変わる暮らし
断熱性能を高めることは、単なる「省エネ」だけでなく、日々の暮らしを大きく変える力を持っています。
- 冷暖房費の削減:エアコンの稼働時間が減り、電気代を抑えられる。
- 健康的な住環境:冬のヒートショックを防ぎ、体への負担を軽減。小さなお子さまやご高齢のご家族も安心。
- 結露・カビ対策:室内の表面温度が安定することで、窓や壁に水滴がつきにくく、カビやダニの発生を抑えられる。
- 家の寿命を延ばす:結露や湿気による構造材の劣化を防ぐことで、家を長持ちさせることができる。
最後に
家づくりでは、キッチンやお風呂、外観デザインなど、目に見える部分にどうしても意識が向きがちです。もちろん、それも大切な要素です。毎日暮らす家だからこそ、使いやすさやデザイン性にはこだわっていただきたいと思います。
ただ同時に、「断熱性能」についても十分に配慮することが欠かせません。断熱は一度建ててしまうと後から大きくやり直すことが難しい部分です。見えない性能ですが、暮らしの快適さ、健康、光熱費、そして家そのものの耐久性に直結します。
当社では C値0.5以下・UA値0.4以下 を目標とし、静岡の気候に合った「高気密高断熱の標準仕様」を採用しています。冬は暖かく、夏は涼しい、そして一年を通じて快適に暮らせる住まいをご提案しています。
これからも皆さまにとって役立つ情報を少しずつお届けしていきますので、ぜひ家づくりの参考にしていただければ幸いです。